ラウドバジェッティングは、2023年末にTikTokで生まれ、2024年から2025年にかけて英語圏メディアで継続的に取り上げられている「予算を声に出して宣言する」節約術です。
発端動画は150万回超の再生を集め、#LoudBudgetingの累計視聴は2025年初で約1,300万回規模と報じられています。従来の「お金の話はタブー」という考えを覆し、予算を堂々と宣言することで節約を成功させる新しいアプローチが注目されています。
ラウドバジェッティングとは?基本的な意味と特徴
ラウドバジェッティング(Loud Budgeting)とは、自分の予算や財務目標を公に宣言し、不要な支出を避けるための節約手法です。予算・金銭目標を公言して境界線を明確化し、ムダ出費を避ける実践として定義されています。
この手法の最大の特徴は、節約を「恥ずかしいもの」ではなく「かっこいい選択」として位置づける点にあります。友人からの高額な誘いに対して「予算オーバーなので今回はパス」と堂々と言えるマインドセットを作り上げることが目的です。
Quiet Luxuryとの明確な対比
Quiet Luxuryが”静かな高級志向”なら、ラウドバジェッティングは”等身大の節約を堂々と表明”する概念です。「贅沢より安定」へ価値観がシフトした若年層に支持されました。
Quiet Luxuryが高級品を控えめに楽しむ富裕層の美学だったのに対し、ラウドバジェッティングは一般人が実践可能な節約を積極的に宣言するムーブメントとして対極に位置しています。
TikTokから世界へ広がった背景と経済事情
バイラル化のきっかけ
ラウドバジェッティングの起源は、2023年12月にTikTokクリエイターのLukas Battleが投稿した動画です。彼が「Quiet Luxuryの反対」として提唱したこの概念は、その後英語圏を中心にメディアで継続的に取り上げられています。
米・英を中心に報道が広がり、Axios、The Guardian、Bloomberg、Fortuneなどの主要メディアで特集されました。2025年時点でもその有効性が認められ、継続的なトレンドとして評価されています。
Z世代を取り巻く経済状況
このトレンドの背景には深刻な経済事情があります。Deloitte 2025年調査によると、コスト・オブ・リビング(生活費)はZ世代の最重要懸念となっており、過半数がペイチェック・トゥ・ペイチェック(給料日までギリギリの暮らし)状態と回答しています。
具体的な状況:
- 3分の1超が生活費の支払いに苦労
- 物価上昇圧力は続く(米国の直近CPIは前年比+2〜3%台)
- 学生ローンや住宅費の高騰が若者世代を直撃
こうした状況下で、若年層は従来の消費行動から計画的な節約へと行動を変化させています。
海外での実践方法と成功事例
基本的な5つのステップ
海外メディアで推奨されているラウドバジェッティングの実践方法は以下の通りです:
- 予算の可視化:収入から必須支出を差し引き、可処分所得を明確化
- 目標の宣言:具体的な貯蓄目標を設定し、周囲に表明
- 断り方のテンプレート化:「Sorry, not in my budget for 2025(今年の予算的に難しいです)」など定型文を準備
- 代替案の提示:高額な誘いに対する別の選択肢を用意
- 定期的なレビュー:進捗を可視化し、必要に応じて共有
実際のSNS投稿事例
効果的な投稿パターン:
- 予算外の誘いを断る例:「今月は旅行予算ゼロ、貯蓄優先モードです!」
- 代替案の提示:「高額ディナーは無理だけど、ホームパーティーはどう?」
- 目標達成の報告:「貯蓄目標達成!ラウドバジェッティング効果あり」
重要なのは具体的な金額ではなく、予算に対する明確な姿勢を示すことです。
活用されているアプリ・ツール
海外で人気の共有機能付きアプリ:
- Honeydue:カップル向け家計共有アプリ、共有する情報を選択可能
- Goodbudget:エンベロープ法による予算管理、家族間での共有機能
- YNAB(You Need A Budget):共有・共同管理機能を備えた予算システム
これらのアプリは共有範囲を調整できる設計により、ラウドバジェッティング実践者のニーズに対応しています。
日本での受け入れられ方と可能性
日本特有の文化的課題
日本では伝統的に「お金の話はタブー」とされる文化があります。三井住友銀行の2025年1月調査では、家族・パートナーにも貯蓄額を伝えない人が67.1%という結果が出ており、金銭オープンネスは依然として課題です。
しかし、若年層ほど共有に抵抗が薄い傾向も示されており、Z世代では変化の兆しが見え始めています。
国内アプリの対応状況
共有機能付き家計アプリの進化が追い風となっています:
主要な国内アプリ:
- マネーフォワードME:2025年9月9日に「シェアボード」機能を開始。必要な金融機関のみ選択して共有可能
- Zaim:2024年11月リリース、2025年2月に機能拡充された「ペア家計簿」で共有したい口座のみを選択公開
これらは共有する口座・情報を選べるため、段階的な”声出し節約”の実践に適しています。プライバシーを保護しながら透明性を高められる設計が特徴です。
普及の可能性と変化の兆し
日本での普及を示唆する要因:
- 節約系YouTuberの人気拡大
- Z世代の70%が節約意識を持つ(国内調査)
- 「メリハリ消費」として趣味に投資、日常で節約する傾向
- SNSで節約情報を共有する若者の増加
2025年中に独自の「ラウドバジェッティング文化」が形成される可能性は高いと予測されます。
実践時の注意点とプライバシー対策
個人情報漏洩のリスク
ラウドバジェッティングの実践には以下のリスクが伴います:
主要なリスク要因:
- 詐欺のターゲット化:収入や貯蓄に関する情報の悪用
- アプリのデータ共有:研究では家計簿アプリの60%が何らかのデータを第三者と共有していたとの指摘
- 過度な情報公開:SNSでの詳細な財務情報共有による被害
推奨される安全対策
FTC(米国の消費者保護機関)推奨の基本策を含む対策:
- 2要素認証の徹底:すべての金融関連アプリで必須化
- 共有範囲の最小化:信頼できる友人・家族のみに限定
- 抽象的表現の使用:「貯蓄目標達成」など具体的金額は非公開
- 定期的な設定見直し:プライバシー設定の確認と更新
専門家からの警告
注意すべき副作用:
- SNS発金融アドバイスの危険性:情報の真偽確認が重要
- 社会的孤立リスク:過度な節約宣言による人間関係への影響
- 同調圧力:周囲の評価を気にしすぎることによるストレス
情報の真偽確認と適度なバランス感覚を保つことが重要です。
成功のポイントと実践のコツ
日本版ラウドバジェッティングの提案
日本の文化に適応した実践方法:
- 段階的な公開:まず家族から始めて徐々に範囲を拡大
- 目標重視の表現:「○○のために節約中」など前向きな理由を併記
- 代替案の充実:断るだけでなく、別の楽しみ方を提案
- アプリの活用:国内サービスの共有機能を使った透明性の確保
継続のための心構え
- 完璧主義を避ける:100%の実践ではなく、できる範囲から
- 仲間作り:同じ価値観を持つ人とのコミュニティ形成
- 定期的な見直し:生活状況の変化に応じた予算調整
まとめ:ラウドバジェッティングの今後
ラウドバジェッティングは、コスト・オブ・リビングへの不安に直面するZ世代が生み出した実用的な節約術です。従来の「お金の話はタブー」という価値観に変化をもたらし、透明性とアカウンタビリティ(お金の使い方を自分自身や他人に説明できる責任)を重視する新しいアプローチとして2025年時点でも有効性が認められています。
日本での展望
2025年以降の予測:
- 国内家計管理アプリの共有機能充実が後押し
- 節約系インフルエンサーの影響力拡大
- Z世代を中心とした価値観変化の加速
- 独自の「日本版ラウドバジェッティング文化」の形成
実践時の重要ポイント
- プライバシー保護の徹底:FTC推奨の基本策を遵守
- 段階的な導入:無理のない範囲から開始
- 文化的配慮:日本の金銭観に配慮した表現方法
- 継続可能性:完璧を求めず、長期的視点で実践
適切な情報管理とバランス感覚を保ちながら、自分に合った形で取り入れることで、この新しい節約術の恩恵を受けられるでしょう。
物価上昇と若者世代の価値観変化が続く限り、この「声に出す節約術」は今後も重要なトレンドとして定着する可能性が高く、日本独自の発展を遂げることが期待されます。

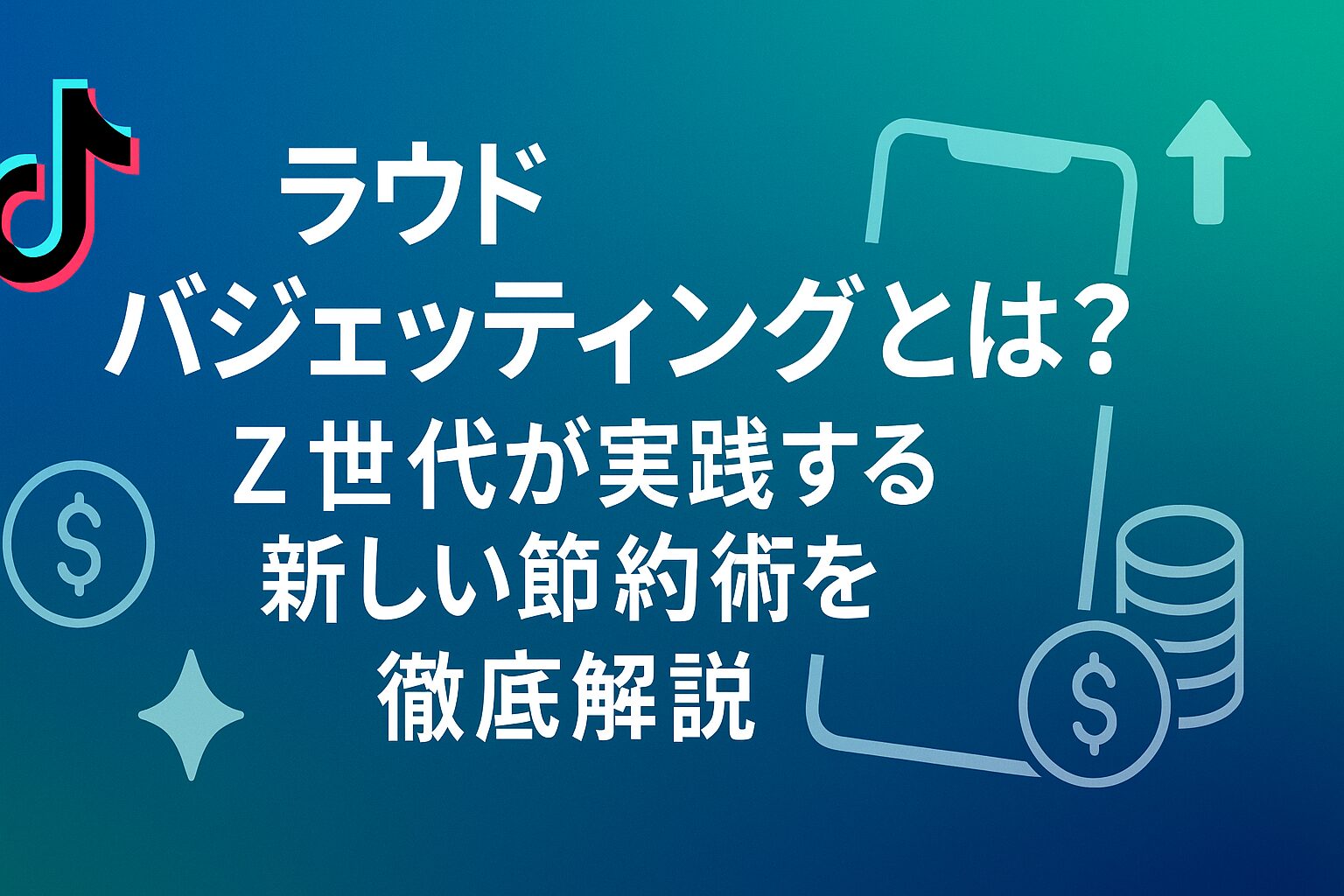
コメント