2025年10月1日から全国で開始予定の「マイナ救急」について、「暗証番号を忘れたら使えないのでは?」と心配している方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、救急現場では暗証番号の入力は原則不要です。救急隊員は顔と券面写真の目視確認で本人確認を行うため、4桁の暗証番号を覚えていなくても大丈夫。ただし、通常の病院受付とは仕組みが異なるため、正しい知識を持って準備することが大切です。
この記事では、マイナ救急の実際の運用方法から事前準備まで、安心して活用するための情報を詳しく解説します。
マイナ救急で暗証番号は本当に不要?【結論:原則不要】
救急現場では目視による本人確認が基本
マイナ救急では、救急隊員がマイナンバーカードの券面写真と本人の顔を見比べて本人確認を行います。このため、4桁の暗証番号(PIN)を入力する必要は原則ありません。
総務省消防庁の公式ページ「あなたの命を守る『マイナ救急』」でも、暗証番号は原則不要と明記されており、宇治市や愛媛県など複数の自治体も同様の案内をしています。
12桁のマイナンバーも使用しない
よくある誤解として「12桁のマイナンバーを見られるのでは?」という心配がありますが、救急活動では12桁の個人番号は一切使用しません。
救急隊が閲覧するのは:
- 券面の基本情報(氏名・住所など)
- 受診歴・診療情報
- 薬剤情報・特定健診情報
税金や年金など、救急活動に関係のない情報は見ることができません。これも消防庁公式で明記されています。
救急現場と病院受付の違い|本人確認方法を比較
救急現場と通常の医療機関では、マイナンバーカードの使い方が大きく異なります。
救急現場での使用方法
- 本人確認:救急隊員による目視確認
- 読み取り:専用端末でカード読み取り
- 暗証番号:原則入力不要
- 同意確認:本人同意を基本とするが、緊急時は特例あり
病院・薬局での通常使用
- 本人確認:顔認証付きカードリーダー
- 認証方法:顔認証成功時は暗証番号不要、失敗時は4桁PIN入力
- 同意確認:患者の明確な同意が前提
この違いを理解しておくことで、「病院で暗証番号を求められた」という体験があっても、救急時は別の仕組みだと安心できます。
意識不明でも大丈夫?同意が取れない場合の対応
緊急時の特例措置
意識不明や重篤な状態で本人の同意が取れない場合でも、「生命・身体の保護のために必要」と判断されれば、同意なしで医療情報を閲覧できます。
この特例措置は個人情報保護法に基づく運用で、厚生労働省のQ&Aでも明記されています。アクセス権限は院内の管理下で限定され、すべての閲覧記録が残されます。
家族の同意は必須ではない
「家族がいないと使えないのでは?」という心配もありますが、家族の同意がなくても、緊急性が認められれば情報閲覧が可能です。
ただし、家族が現場にいる場合は、できる限り説明と同意確認を行うのが基本の流れとなります。
透明性の確保
誰がどこで医療情報を閲覧したかは、マイナポータルで本人が後から確認することができ、透明性が保たれています。
マイナ救急で見られる情報・見られない情報
閲覧できる医療情報
マイナ救急で救急隊や搬送先の医療機関が確認できるのは:
基本情報
- 氏名・住所・生年月日
- 保険者情報
医療関連情報
- 過去の受診歴・診療情報
- 処方された薬剤情報(レセプト由来)
- 特定健診の結果・手術情報
- レセプト等のデータや電子処方箋の調剤情報等を基にシステム側で集約された「救急用サマリー」
対象外の情報
以下の情報はマイナ救急では閲覧できません
- 市販薬(OTC)の購入履歴(保険請求データに含まれないため)
- サプリメント等の服用状況
- 税務・年金等の情報(そもそもカードのICチップに入っていない)
- その他救急活動に関係のない個人情報
情報の範囲が限定されているため、プライバシーへの配慮がされています。
今すぐできる準備|カード登録と携行のポイント
必須の事前準備
マイナ救急を利用するには、以下の準備が必要です:
1. マイナンバーカードの取得
- まだ持っていない場合は申請手続きを
2. 健康保険証利用の登録
- マイナポータルまたは医療機関等で登録
- 「マイナ保険証」として使える状態にする
3. カードの携行
- 外出時はマイナンバーカードを持ち歩く
- カードがないと救急現場で利用できません
家族分の準備も忘れずに
子ども(15歳未満)
- スマホ保険証は原則利用不可
- マイナンバーカード+保険証利用登録が必須
高齢者
- 家族がカードの保管場所を把握
- 保険証利用登録の完了を確認
スマホ保険証は救急で使える?
2025年9月19日から準備の整った医療機関・薬局でスマホ保険証の利用が順次開始されました。ただし、救急現場での利用に関する公式案内は現時点で確認できません。
消防庁の案内では「マイナンバーカード所有+保険証利用登録」が必要と明記されており、確実にマイナ救急を利用するためにはマイナンバーカードの携行が推奨されます。
カードの安全な携行方法
「カードを持ち歩くのは危険では?」という心配もありますが:
- ICチップには高度な偽造対策が施されている
- 暗証番号によるロック機能がある
- 税・年金等の情報はそもそもカードに入っていない
適切に管理すれば、安全に携行できます。
よくある誤解を解消|12桁番号・プライバシー・スマホ保険証
誤解1:「12桁の番号を救急隊に見られる」
正解:12桁のマイナンバーは救急活動では使用しません
救急隊が利用するのは券面の基本情報と医療関連データのみです。消防庁公式でも明記されています。
誤解2:「プライバシーが全て筒抜けになる」
正解:閲覧できる情報は医療に関連するもののみ
税金、年金、その他の個人情報は見ることができない仕組みになっています。さらに、アクセスログはすべて記録され、マイナポータルで確認可能です。
誤解3:「市販薬やサプリの情報も見られる」
正解:市販薬(OTC)は原則対象外
薬剤情報は保険請求データ(レセプト)由来のため、保険適用外の市販薬やサプリメントは記録されません。
誤解4:「スマホがあればカードは不要」
正解:救急現場ではカードの携行が確実
スマホ保険証は医療機関・薬局で順次利用開始されていますが、救急現場での利用可否は公式に案内されていません。
誤解5:「家族の同意がないと使えない」
正解:緊急時は同意なしでも閲覧可能
生命・身体の保護に必要と判断される場合は、個人情報保護法に基づく特例措置により、本人・家族の同意がなくても医療情報を閲覧できます。
まとめ:マイナ救急を安心して活用するために
2025年10月1日から全国で開始
マイナ救急は2025年10月1日に全国一斉開始され、720消防本部・5,334隊(常時運用救急隊の98%)が対象となります。
重要なポイントまとめ
暗証番号について
- 救急現場では原則入力不要
- 目視による本人確認が基本
- 消防庁公式で明記済み
事前準備
- マイナンバーカード取得+保険証利用登録
- カードの携行が必要(スマホ保険証の救急対応は未案内)
- 家族分の準備も忘れずに
安心・安全な仕組み
- 閲覧情報は医療関連のみに限定
- 意識不明時も適切に運用される特例措置
- アクセスログの記録・透明性の確保
- 高度なセキュリティ対策
期待される効果
従来は本人や家族から病歴・服薬情報を聞き取る必要がありましたが、マイナ救急により:
- 搬送先選定の迅速化
- 医療機関での事前準備
- 適切な応急処置の実施
これらの改善が期待されています。
今すぐ始められること
まだ準備ができていない方は:
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録を完了
- カードを普段から携行する習慣を
- 家族分の登録状況も確認
正しい知識を持って準備すれば、マイナ救急はいざという時にあなたや家族の命を守る重要なツールになります。不安や疑問があった方も、この記事の情報を参考に、安心してご利用ください。
出典・参考
- 総務省消防庁「あなたの命を守る『マイナ救急』」
- 厚生労働省「救急時医療情報閲覧 概要案内」
- 厚生労働省「スマートフォンのマイナ保険証利用について」
- 各自治体公式サイト(宇治市、愛媛県ほか)
※本記事は2025年9月22日現在の情報に基づいて作成されています。

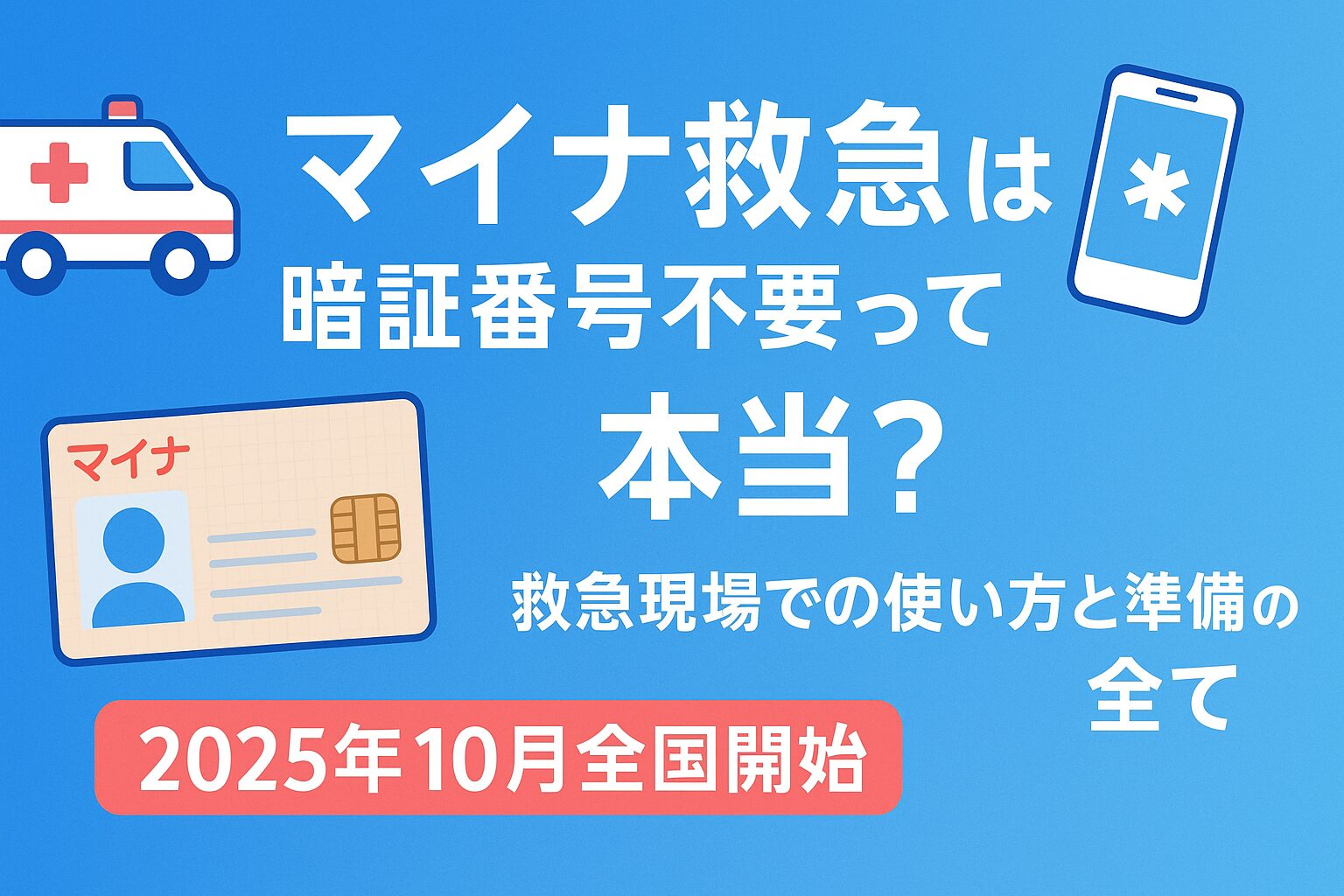
コメント